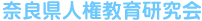2016年度 あいどるとおく

10月号 「家庭訪問」
人権教育が最も大切にしている原則は、「差別の現実に深く学ぶ」ことです。私が教員駆け出しの頃、先輩教員から教えられました。「現実」、「深く学ぶ」とは、どういう意味だろうと自問自答していた頃、当時担任したある中学生の家に何度となく家庭訪問をすることがありました。
担任をしていたその少女は、学期の途中で大阪から転校してきました。父と2人暮らし、欠席や遅刻の日々が少なくありませんでした。ある日、午前中に授業がない時間に家に行くと、晩秋の寒い部屋に火の気はなく、電気も灯けずに、父親のものであろう洗濯物をたたんでいました。学校での「つっぱった姿」からはすぐに想像できなかった自分の中に、驚きを禁じ得なかったとともに、自分自身の小ささを反省しました。そこには、少女の「現実」がたくさん転がっていたのです。「ゆうべも、おとん、また酒飲んで、いらんかった、せやけどなぁ~うちがおらんと・・・」何度か通っているうちに、そんな話もポツリ、ポツリ聞かせてくれました。朝、家まで様子を見に行くことも何度かありました。しばらく話した後、今日はどうする?と水を向けると、「行くわ」と言うときもあれば、「休む」という日もありました。少女の身の上に家族の「生活」というものが重くのしかかっていることに、何ともすることができない自分に無力さを感じたこともありました。少女は学校へ来ても決して「おとなしく」しているわけではありませんでした。何かと問題を起こしました。
こうした学校で見せる姿は、「自分のことを分かってほしい」という合図だったということに気づけたのは、「現実」に「学んだ」からだと、振り返ってみて強く思います。この「学び」を元に、体を張って関わり続けることに取り組みました。また、心の中にある「本当の思い」を聞いてくれる「つれ」をつくってほしいと、学級の中でつながりをつくる生活を出し合う「集中HR」に取り組みました。そうした取り組みで、少女は少しずつ自分の本当の姿を出してくれるようになりました。教員をして良かったと思う一瞬でもあります。
1962年発刊の「むなつき坂をこえて」には、「教育の風潮がどうあろうと、教育の方針がどう変わろうと、部落がある限りわたしたちはそこから物事を見、考えていくつもりだ。」という一文があります。家庭訪問から物事を見、子どものことを考え、取り組んでいくことは、世の中がどう変わろうとも、人権教育の根幹だと今も確信します。